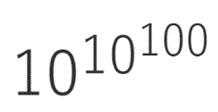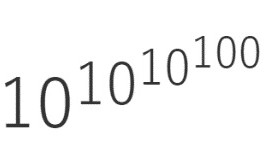今日、こんなことを知りました。体が熱を出すのは、パイロジェンが視床下部の体温の設定値を上げるからです。
発熱は防御機構であり、ほとんどの発熱は、体が細菌、ウイルス、寄生虫に感染したときに起こります。その他、アルコールの禁断症状や熱中症などでも発熱することがあります。
体温を上げるには、代謝コストがかかります。エネルギーが必要なので、そのエネルギーを補給することになるのです。ということは、熱がないよりあった方がメリットがあるに違いない。すべての哺乳類は熱を出すことができるので、有益であることがわかる。熱を出せない魚やトカゲは、感染症にかかったとき、体温を上げるために暖かさを求めます。
では、どうして熱が出るのかを見る前に、その理由を見てみましょう。
インフルエンザなどのウイルス感染症にかかった場合、ウイルスは平熱で最もよく繁殖します。体温が上がると、ウイルスにとって不利な環境になります。体がウイルスを調理しようとするのです。しかし、発熱の有益な理由はこれだけではありません。
感染症と戦うとき、白血球の一種であるT細胞を使う必要があります。このT細胞は、ウイルスを検出するまで血液の中を浮遊しています。T細胞には、ヘルパーT細胞とキラーT細胞の2種類があります。キラーT細胞は、ウイルスを検出すると、その名の通りウイルスを攻撃します。一方、ヘルパーT細胞は一番近いリンパ節に向かい、そこで抗体を持つB細胞と、さらにキラーT細胞の産生を促します。
これが発熱とどう関係があるのだろうか?T細胞は血液の流れからリンパ節に移動しなければならないのですが、私たちの体内の血液はかなり速く動いています。私たちが熱を出すと、熱の上昇によってT細胞が刺激され、2つのタンパク質が作られます。それが、α4インテグリンと熱ショックタンパク質90(Hsp90)です。体温が上昇すると、T細胞はより多くのHsp90を産生する。Hsp90分子が蓄積されると、α-4インテグリンタンパク質を活性状態に切り替えます。そのため、タンパク質は粘着性を持ち、突出した状態になる。マジックテープのフックのようなものです。 これを利用して、T細胞はリンパ節に近い血管をつかみ、そこを通り抜けることができる。
この実験を行うために、Hsp90がα-4インテグリンを活性化できないようにマウスを改造したものがある。そのマウスでは、T細胞がリンパ節に到達することはほとんどなかった。つまり、発熱がなければ、私たちの体は外敵に対する防御を開始することができないのです。
では、私たちの身体はどのようにして熱を出すのだろうか?
それは、視床下部をリセットすることによって行われます。視床下部は脳の底部にあり、空腹感、喉の渇き、愛着行動、疲労、睡眠、概日リズム、体温などを司っている。視床下部は、体温に関して、暑いか寒いかの2つの選択肢を持っています。体が熱すぎると、視床下部は汗をかいて体を冷やし、寒すぎると、視床下部は震えなどの反応を起こして体を温めようとします。
ウイルスや細菌が体内に侵入すると、パイロジェン(発熱物質)を放出します。これらのパイロゲンは血液を介して脳に移動し、脳はプロスタグランジンE2(PGE2)を生成する。このPGE2が視床下部と相互作用し、視床下部は体温の設定値を2~3度上方に調整する。
視床下部が新しいセットポイントを設定すると、その新しいセットポイントまで身体を温めるために、さまざまな生理的変化が起こり始める。
血管が収縮し、皮膚からの熱損失が減少する。副腎からノルエピネフリンが放出され、褐色脂肪組織を燃やして熱を発生させる。体の代謝率が上がり、血液が四肢から暖かい体幹に移動する。筋肉はエネルギーを消費するために収縮を始め、これが震えとなる。
発熱は、ウイルスや細菌が対処されるまで続きます。細菌やウイルスが体内からいなくなるまで、パイロジェンを生成し続け、パイロジェンは脳にPGE2を作り続けさせ、視床下部のセットポイントを高く保つ。パイロゲンがなくなり、PGE2の産生が止まれば、体温のセットポイントは正常に戻ります。
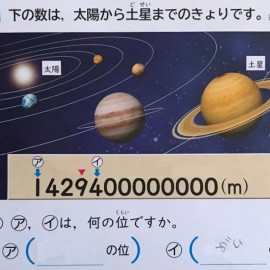
 (じょ)
(じょ)