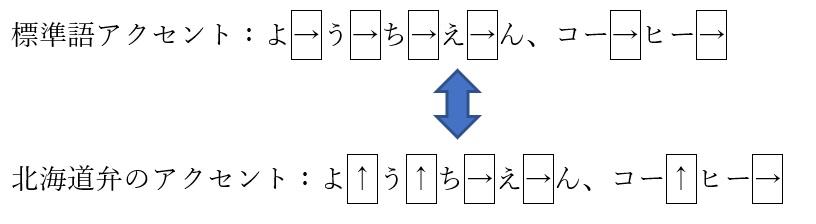最近再確認できたことですが、インスピレーションというものは伝染するのです。私にとってはこれはとてもラッキーなことです。校長になったばかりの私にとっては毎日なれない事ばかりで時間を過ごしていますから、周りの人からインスピレーションを受けることによって助けられていることがあります。自然の美しさからインスピレーションをもらうこともあって、雪をかぶっている山や夕日で桃色になっている空やずっと眠っていた枝の先っぽに出てきている若緑によって気持ちが和らぐ事もよくあります。でも、私にとって最も刺激を受けるのは人間です。その中でも、一番心に響くのは一緒に過ごしている人たちから受けるインスピレーションです。
今週、私の心を高揚させてくれたのは周りにいる生徒や教員の言葉でした。月曜日に新入生のプログラムで学校の歴史について講演をすることになりました。北星女子が大切にしている価値観の一つとして「つながり」がありますから、生徒が学校の歴史と個人的繋がりを感じることができる活動をしようと思いました。北星を形作った宣教師の先生方について、それぞれの先生が何をしたかだけではなく、それぞれの行動から伝わってくる先生方の性格についても話しました。その話の中で、新入生には自分と一番近いつながりを感じる先生はどれでしょうかという質問について考えてもらいました。その関連性は今の自分と似ているということでも、その先生のようになりたいということでもいいと説明しました。生徒の書いたことを読んで、スミス先生とモンク先生とエバンス先生のことを新たな目で見ることができました。
特に印象的な生徒の回答としてはこんなのがありました:
● スミス先生…誰かのために努力をして結果を出していたのが凄いと思った。私もこんな風に誰かのためになることをしてみたい。
● スミス先生…目的地がどんな場所か分からなくても、自分がやりたいことに全力になれて、それを実現させているのが尊敬できる。
● モンク先生のようになりたい。誰もが嫌がることでも大切なことだからと自分で積極的に行動するという。周りを思いやる、支える姿勢が素敵だと思った。また、世の中を知るためなど、自分の目的に向かって努力できる人になりたいと思った。
● モンク先生のような人間になりたいと感じた。一度何かに挑戦して失敗したら、何度も再挑戦してみることの重要さを再認識させられた。
● エバンス先生の活発なところが自分と似ているかなと思いました。厳しさよりも愛情の方を大事にしていきたい。他人のために愛のある行動をとれるようになりたい。生徒のこういう声を聴いて、それぞれが学校の歴史とのつながりを見つけて、そこから自分の未来に向けて頑張る力を得たことに、教員として感動しました。
これを読んで、私もいろいろ頑張りたくなりました。皆さんにとっては、どれが一番感動的でしょうか。
今年度から一つ新しい取り組みを始めました。先生方が忙しい中でさらに仕事が増えるようなお願いをすることは気になりましたが、校長として一番大切な役割の一つは教職員一人ひとりの活躍を支援することだと考えると、一人ひとりが頑張りたいところが分からなければ、その役割を果たすことができないと考えました。そこで先生方の今年度の個人目標を書いてもらうことにしました。上がってきた個人目標を読むと、それぞれの立場から学校の課題が見えてくるだけではなくて、それぞれの先生から、今年度、生徒のため、学校のためにできる大切なことを教えてもらっている気がします。一人一人が学校の改善についていろいろと考えてくれて、各々が一生懸命に取り組みたいところの説明を読んでいると、私まで感動して、もっと学校のため、先生方のため、生徒のために頑張りたくなるのです。
北星の先生方は今年こんなことに取り組もうとしています。
● 自律した生活習慣を身に付け、自治の精神が根付いた集団作りを行う。
● 女子単学の環境を生かし、自己を受け入れ挑戦できる土壌を構築する。“
● 生徒主体の授業をできる限り取り入れる。教員が話す時間を1授業あたり10分を目標にしたい。
● 日々の声掛け(授業では1時間につき最低10人にあてる
● 生徒たちみんなが楽しく、生き生きと前向きに学校生活を送ることが出来るように努力する。
● 思考/判断/表現力を高める授業の研究、個別最適な学びの研究、ICT活用の研究
このように、一人ひとりの教員の、自分が鍛えたいところ、生徒のために工夫したいところを見ると私自身も難しいこと(大変なこと)に取り組む意欲がわいてきます。日本語でブログを書くように精一杯頑張らなければという気にもなり、久しぶりにSNSに取り組むことを決心しました。生徒や教員からの言葉に触れることによって、元気をもらうだけではなく、自分自身、教員(教育)として働くことができる機会を与えられていることが光栄なことだということに気が付きました。学校で働いていると毎日周りの人からインスピレーションをもらう出会いの可能性があります。その日その日の日常的な交流から刺激や元気をもらうことができます。そのために周りに目を向けて、しっかりと色々な人の声を聴き、心を込めて質問をし、その答えを心にとめておかなければならないと感じます。
毎日交流してくれる生徒たち、先生たち学校関係者の皆さまに改めて感謝したいと思います。皆さんは私が毎日仕事に来る理由になっています。皆さんからもらうインスピレーションの火花のおかげで、毎日少しずつ、皆さんが必要としているこの場所、皆さんが毎日元気よく楽しく通うことができる今の時代に合った学校の校長になれるように精一杯頑張りたくなります。力を合わせて、輝く未来に向けて一緒に頑張りましょう!
Inspiration is contagious
Inspiration is contagious – which is good for me, because I need all the inspiration I can get! I am in a new position, one that builds on the work I have been doing for years as an educator. While I do get inspiration from natural beauty – snow-capped mountains, pink sunsets, budding trees – for me, people are always the source of my inspiration. More specifically, I am inspired by people I know.
Recently I have had two chances to be inspired by those around me, and since I work in a school, the sources of my inspiration have been students and teachers. Earlier this week I was scheduled to speak to the student body for an hour about the history of our school. I was to give the second of three hour- long presentations. I have been a classroom teacher for 35 years, and I love the energy I get back from students, so I wanted to find a way to give the presentation that would energize both me and the students. I decided to tell stories about the three teachers who played a key role in our school’s past and challenge students to connect personally with one of the three teachers, to find someone they felt was similar to them or someone they wanted to become like.
I was inspired by the students’ responses:
● I thought it was amazing that Sarah Smith worked so hard to achieve things that would benefit others. I would also like to do something useful for others like this.
● I admire Miss Smith. Even though she didn’t know what her destination was, she put her all into everything she did so she could realize her goals.
● I want to be like Alice Monk. She took the initiative to engage in tasks that no one else wanted to do because she understood how important they were. I was impressed by how considerate and supportive she was of people around her. Like Miss Monk, I want to become someone who can strive towards my own goals, such as learning about the world.
● I want to be like Miss Monk. I was reminded of the importance of trying again and again even if I fail the first few times.
● I thought Elizabeth Evans’s active personality was similar to mine. She valued love more than strictness. Like her, I want to be able to act lovingly for others. From these responses, I could see that students were really trying to make a personal connection to our school’s past – to look to our shared past to find inspiration for their own futures.
I have also asked teachers to take on a new initiative this year – to set a personal goal for the year. I am hesitant to ask teachers to do something extra at a time when they are already so busy. At the same time, I believe that the most important thing I can do as principal is to support teachers in the things that matter most to them. By reading teachers’ goals, I get insight into what matters to them. And because I know how busy they are, I am all the more inspired by this insight into how each teacher saw themselves as an invaluable cog that keeps our school running through their unique contributions.
Here are a few of the responses that inspired me:
● Help students develop independence and build a class grounded in student autonomy.
● Take advantage of the all-girls’ environment to create an atmosphere where students can accept themselves and take on challenges.
● Incorporate student-centered classes as much as possible. I would like to aim to talk for only about 10 minutes per class. I also want to call on students more in class (so they have more chances to participate in the learning).
● Strive to ensure that all students experience school as fun, lively, and positive
● Research classes that improve thinking/judgment/expression skills; research optimal individual learning, and effective uses of technology in the classroom
When I see these examples of people challenging themselves, pushing themselves to do more, it inspires me to try things that are hard – things like publishing a blog in Japanese and diving back into social media to share my everyday inspiration with others. It also helps me to realize how lucky I am. Working in a school, I am surrounded every day by people who can be a source of inspiration to me, if only I take the time to look around, to listen, to ask questions, and to care about the answers.
In closing, I want to offer sincere gratitude to the teachers and students I work with every day. You are the reason I come to work each day, and your sparks of insight push me to become a better version of myself day by day as I strive to become the principal who will make you want to come to school every day. So, thank you! I couldn’t do it without you!!!